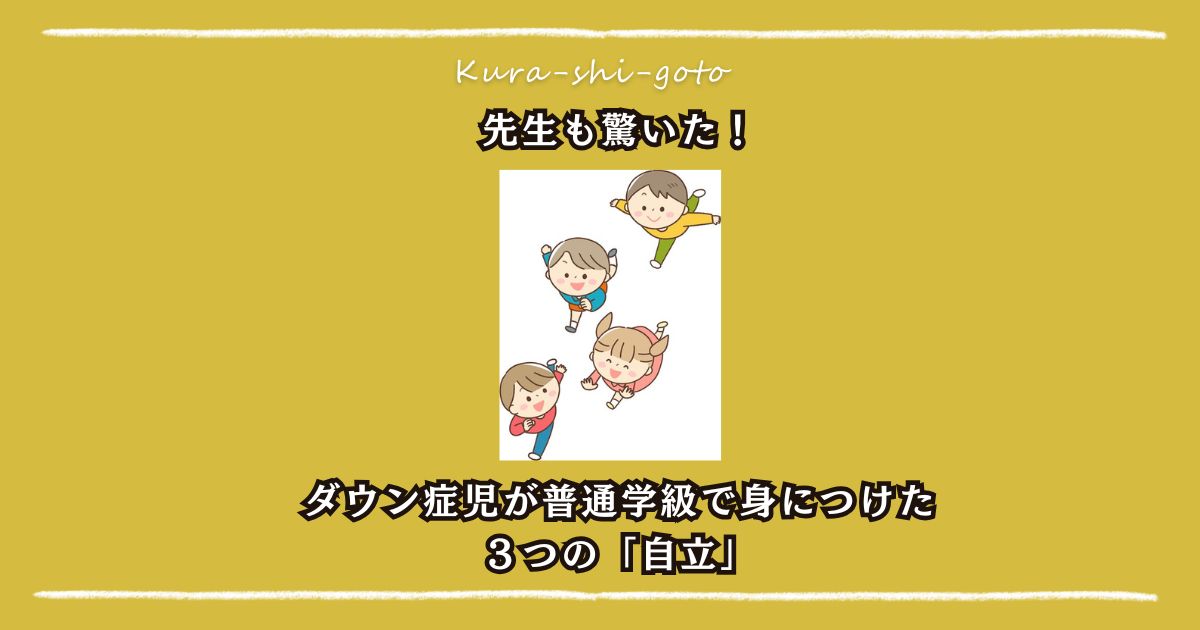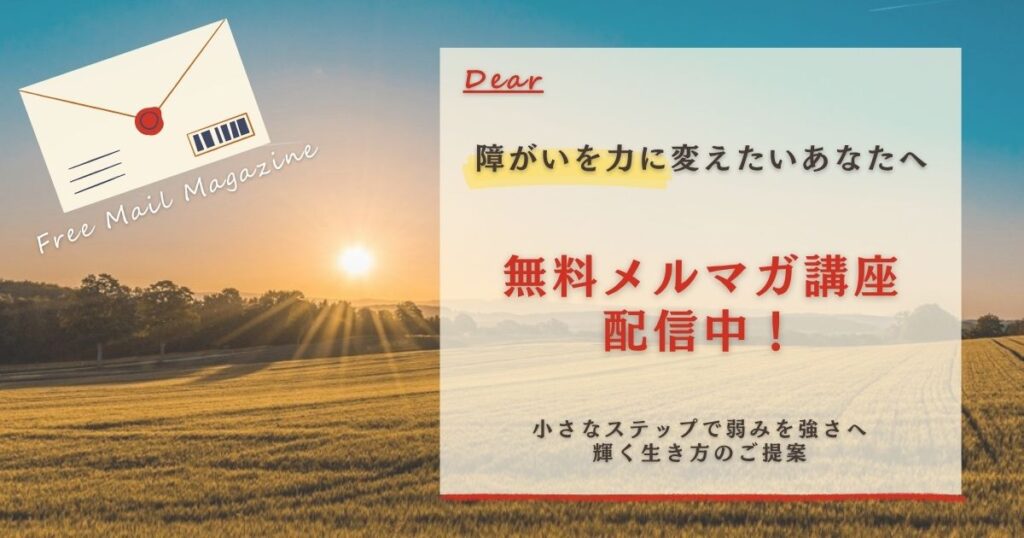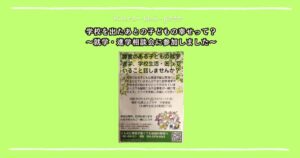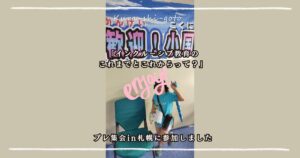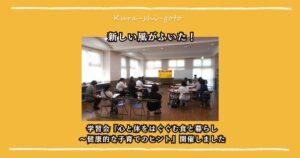- 普通学級では、生活自立の授業がないけれど、自立の力は身につくの?
- 大人がマンツーマンでつかないと、危ないんじゃないの?
- 誰がお世話をしてくれるの?
このような疑問を持つ方にオススメの記事です。
普通学級に通う娘は、小学校3年生になり3ヶ月を過ごして、教育相談の時期になりました。
担任の先生も驚いた、娘が身につけている3つの「自立」ついてお伝えします。
身の回りのこと

 先生
先生授業の準備や、プールの着がえ、給食のお支度。
自分でする力が高いです。
時間に限りがあるので、急かしてしまうこともありますが、ゆっくりやれば最後まで自分でできるのでしょうね・・・。
特別支援学級では、着がえやお片付けなど、身の回りのことを練習する時間が、授業の中でありました。
普通学級では、それがありません。
娘は普段の生活の中で、「自分でやってみる」ことをずっと積みかさねてきました。
言葉や数の理解も、ゆっくりではあるけれど、生活で使う中で身につけてくれると思っています。
危険の避け方





休み時間に鬼ごっこをする時は、喜んで行きますよ。
危ない中には入らずに、隅っこの方にいて入ったり出たり、自分でうまいこと調整しています。
学校では、大人がずっと近くについている必要はないそうです。
先生は、周りの子にも気をつけるようにと、日々声をかけてくれています。
子ども同士の育ち合いの中で、大人は近づきすぎず遠くから見守ってくれることが、とても大切だと思っています。
周りを見て聴く力
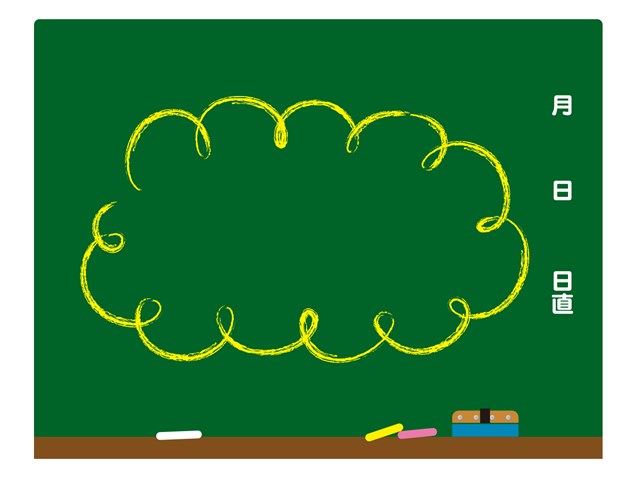
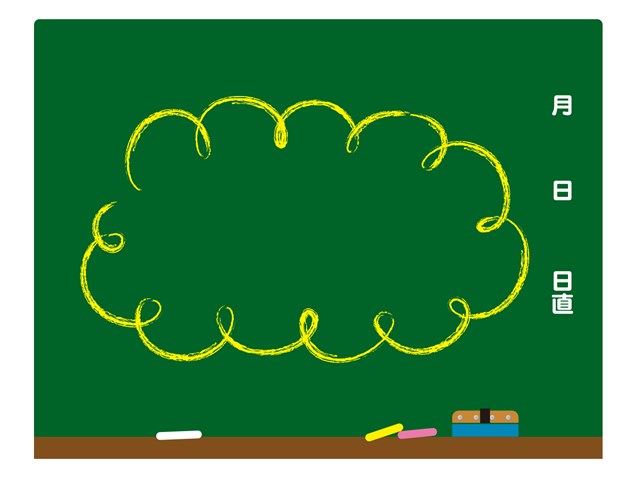



日直当番で、何にも声かけしなくても黒板にこれ(日付けと目標)を書いたんです。
周りがやっていることを、とにかく見て、聴いているんですよね。
特別支援学級では、その子のために調整された環境を、大人が用意してくれました。
普通学級では、集団のペースで物事が進んでいきます。
多くの子どもにとって、ハードな環境ではありますが、娘もその中で、自分にできることは考えてやっているようです。
おわりに ~ありがとうの力~



何よりも、この笑顔と、「ありがとう」が言えるのが良いですね。
クラスの子は、本当に気の良い人達ですよ。
ささーっと、みんなで手を貸してくれますよ。
ありがとうの力で、娘のまわりに笑顔が広がるのを、私も何度も経験しています。
自分でやってみる力
人に助けてもらう力
「自立」とはそんな事なんだろうな。
先生の言葉を聴いて、そう思いました。